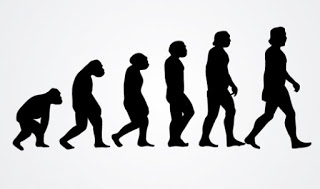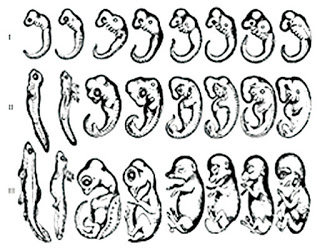ゲイツもザッカーバーグも推す、今読んでおきたいビジネス書ランキングにも入ってくる、巷で話題のユバル・ノア・ハラリ著・柴田裕介訳「サピエンス全史」上下巻を一気に読了。うん、確かに面白かった。こんなにもわかりやすい言葉で(翻訳もすばらしい)、発想の転換、既存の価値観を疑うことを読者に体験させるとはものすごい読み物だ。全史とあるけれども歴史を詳述したものではなく、ホモ・サピエンスが認識革命により想像上の概念を扱えるようになり、実体のないもの、コミュニティ、国家、宗教、イデオロギーとともに時代をたどってきた様を述べる。貨幣さえも「信用(クレジット)」に支えられているのだ。最後にはそんじょそこらのSFなんてものを超越した、今後のサピエンスの行く末は、もはやサピエンスという種(生命)を超えた存在に至るかもしれないという驚きの着地。これをこんなにもわかりやすく、しかも具体例を挙げて説明しているんだから見事としか言いようがない。一読を強くお勧めする。
個人的には上巻が際立って面白くて、下巻に入ると、あぁこの話は知っているけれどもなるほどそういう見方をするのね、で結論はそんなところに落ち着いたかという感じ。まぁ、結論は想像の域を出ていないけれどもね。それは分からないといいながら次の段ではそれを事実として話を進めるなど一部牽強付会なところもある。「既婚者が独身者や離婚した人たちよりも幸せであるのは事実だが」って「事実」なんだ(笑)。一番残念だったのは、キーワードでもあるサピエンスの「幸福」の定義があいまいなことかな。何をもって幸せというのか、もちろん著書の中でそれは一概には決められないと言い、「幸福度」を調査したレポートの紹介はあるけれども、あなた(=著者)が言うところの「幸福」とか指標としての「幸福度」ってなんやねんとつっこみたい。
■ サピエンス全史(上) 文明の構造と人類の幸福 [ ユヴァル・ノア・ハラリ ]
■ サピエンス全史(下) 文明の構造と人類の幸福 [ ユヴァル・ノア・ハラリ ]