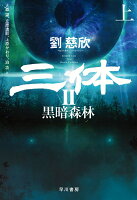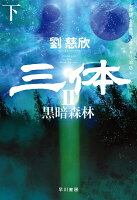物理学者の父を文化大革命で惨殺され、人類に絶望した中国人エリート科学者・葉文潔(イエ・ウェンジエ)。失意の日々を過ごす彼女は、ある日、巨大パラボラアンテナを備える謎めいた軍事基地にスカウトされる。そこでは、人類の運命を左右するかもしれないプロジェクトが、極秘裏に進行していた。数十年後。ナノテク素材の研究者・汪森(ワン・ミャオ)は、ある会議に招集され、世界的な科学者が次々に自殺している事実を告げられる。その陰に見え隠れする学術団体“科学フロンティア”への潜入を引き受けた彼を、科学的にありえない怪現象“ゴースト・カウントダウン”が襲う。そして汪森が入り込む、三つの太陽を持つ異星を舞台にしたVRゲーム『三体』の驚くべき真実とは?本書に始まる“三体”三部作は、本国版が合計2100万部、英訳版が100万部以上の売上を記録。翻訳書として、またアジア圏の作品として初のヒューゴー賞長篇部門に輝いた、現代中国最大のヒット作。
今巷で話題の中国発SF大作。中国のSFかぁ、どことなく前時代的な硬派のSFなんだろうなぁという先入観を持って読みはじめたのだが、全然違っていてすこぶる現代的なエンターテイメント性にあふれたジェットコースター小説で、やたらめったら面白かった。なるほどヒットするのもうなずける。
※ネタバレしないようにという配慮はしないので、以下を読む方はお気を付けください。
物理学の世界に「三体問題(three-body problem)」というものがある。1つあるいは2つの物体の関係は運動方程式で明らかにすることができるが(ニュートンによる)、3つの物体の運動を数学的に解くことはできない。もし太陽が3つある星に文明があればどうなるか(3つの太陽の動きは計算ではわからない)というのが著者の発想のスタート地点だったそうだ。
■ 三体問題(さんたいもんだい)とは – コトバンク
前半は主人公の一人葉文潔の半生や、著名な理論物理学者の相次ぐ自殺や、正体不明の団体や集団、もう一人の主人公汪森にふりかかった不思議な現象(「ゴースト・カウントダウン」のくだりは「リング」っぽくてむしろオカルトだ)、謎のVRゲーム「三体」の世界観などが描かれる。後半では、これらが何なのか、どう関係しているのかが明らかになってくる。簡単に言うとこの作品は異星人地球侵略型のSFなんだけれども、作中では最後まで地球人は異星人とは直接対峙していない。それどころかこの宇宙からの侵略者が地球にやってくるのは、なんと450年後なのだ(本作は三部作の第1部)。光速は有限で宇宙は広いんだけれども、なんだこのリアル設定は。
技術跳躍が生じる可能性が最も高い分野は以下のとおり。
(一)物理学:【略】
(二)生物学:【略】
(三)コンピュータ科学:【略】
(四)地球外知的生命体の探査(SETI):
これらの科学知見がコアになったSF作品であるが、物理学と地球外知的生命体探索はもちろん重要。生物学に関しては環境生態学に関する話題が出てくる(今のところ遺伝子とか生殖とかは表立って出てきていない)。コンピュータ科学に関してはVRゲーム「三体」の中の一シーン(秦の始皇帝)や、三体人(異星人)の科学技術描写でAIが出てくる。とにかく科学のテクニカルタームがわんさか出てくるけれども、知っていれば「なるほどね」とニヤっとできるが、知らなくてもまぁ問題なく読み進められるだろう(知っていなければ筋が追えないということはない)。主人公の一人葉文潔を天体物理学の基礎科学(理論)研究者とし、もう一人の主人公汪森をナノテク素材の応用科学研究者としているところがおもしろい。
エンターテイメントとしては一級だが、作品としては穴が目立つ。捨てキャラ(ほぼ一度限りの登場で物語の本質に影響を与えるほどの役目は担っていない人物)の扱いが笑っちゃうほど適当。なぜか退場後に死までの後日譚まで丁寧に述べられる人物がいる一方で、大事そうに登場したのにその後一切放ったらかしの人物(汪森の家族とか)がいたりする(だったら汪森は独身でも良くね?)。著名な物理学者の相次ぐ自殺の原因も、「え?そんなことで命を絶ったの?科学者だったらむしろそのことを追求しようとしないか?」となぜの嵐。またラスト近くに出てくる三体人が、どうしようもなく地球人似の発想と感情(見た目ではなく)に支配されているのも変。三体人がなぜ地球人とほぼ同じ道徳的価値観を持つのか(科学技術では三体人の方がはるかに進んでいるが)説得力ある説明が欲しい。というか、回収した三体人からのメッセージの存在整合性は物語的に破綻していないか?(ラフにはどういうことなのかよくわからなかった)
ん~~、結局はケチをつけているみたいな書き方になってしまったなぁ。いや娯楽小説としては抜群におもしろいよ。著者の発想のすごさに舌を巻く。ぜひ読んでみて。
■ 三体[劉 慈欣/大森 望]
■ 三体[劉 慈欣]【電子書籍】
原語(もちろん中国語)でチャレンジしてみたいという方はこちらをどうぞ。三部作すべて刊行済み。

近現代の中国を舞台にした作品には頻繁に登場するものの、ラフにとっては今一つ正体がわかっていない出来事が「文化大革命」だなぁ。だから見るたびに、どう位置付けて評価するものなのか悩む。
■ wikipediaの「文化大革命」の項
「ラストエンペラー」の最後にも出てきたよね。個人的に深く印象に残っているのは「レッド・ヴァイオリン」の上海のシーン。
■ wikipediaの「Category:文化大革命を題材とした作品」の項