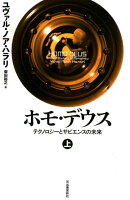

我々は不死と幸福、神性を目指し、ホモ・デウス(神のヒト)へと自らをアップグレードする。そのとき、格差は想像を絶するものとなる。『サピエンス全史』の著者が描く衝撃の未来。生物はただのアルゴリズムであり、コンピュータがあなたのすべてを把握する。生体工学と情報工学の発達によって、資本主義や民主主義、自由主義は崩壊していく。人類はどこへ向かうのか?
歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリによるベストセラーになった前著「サピエンス全史」に続く、人類の行く末の考察。人類の行く末の考察といっても、本著の基本となっているのは歴史的なイデオロギー(宗教)の変遷と、未来の人類の行く末を決定づけるであろう現代科学(バイオテクノロジーとAI)。歴史書というよりも、学術風人類史エッセイ。前著「サピエンス全史」の最後は、人類は有機生命体を脱して電脳空間へと意識のみを移す進化を遂げる可能性があるというびっくりのSF着地だった。さて、今度はどうなるか。ちなみに「サピエンス全史」を読んだ時の感想文はこちら。
読了:サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福 [ ユヴァル・ノア・ハラリ ]
ユヴァル・ノア・ハラリって功成り名遂げた学者かと勝手に思っていたけれども、1976年生まれだというから、ラフより年下だったのね。歴史学者だけれども、進化生物学者的な科学的視点も多くあるところがおもしろい。
現生人類(ホモ・サピエンス)はホモ・デウス(「デウス」は神の意)に進化するのか、2001年宇宙の旅のスターチャイルドみたいななにかに?(表紙の絵から連想)なんて読み始める前は勝手に思っていたけれども、違いました。
現時点(21世紀初頭)で人類が克服したものとして「飢饉」「疫病」「戦争」が挙げられる。すっかり解決できたわけではないものの、対処可能な課題に変わったのだ。そして、これからの人類は「不死と至福と神性を目指して進む」のだろうという仮定のもとにストーリーは進む。
さて、人類も動物であるのだが、なにが人類と他の動物を異なるものとしているのかという点から始まる。動物にも意思(事態の予測さえ可能)と思しきものを持つ種もいるのだ。ただ人類は、実在しないものである概念(神(宗教)、国家、貨幣価値、企業)、そしてそれを他者と共有し協力することが可能で(ん?なんかそういう本を最近読んだぞ?)、これが人類を特別な存在にしたのである。また時間空間を超えて伝える手段である書字さえ身に着けたのだ。
原始的なアニミズムからやがて体系だった宗教というものを生み出した。人は「神」(あるいは神の意志を伝える権威をもった教皇や皇帝、王など)が命ずるからそれを自身の生きる指針とした時代が科学革命の時代まで続く。そして啓蒙主義の時代に入り、誰もが個別に持っている個人の意思というものが重視される人類至上主義の時代に変わる。「神は死ん」で、「私がそう思う(感じる、考える)からだ」ということを明言する時代になったのだ。そして20世紀に自由主義というものが主流になるのであるが、ここにおいて人類至上主義の極端な進化形である「ファシズム」と「共産主義」も生み出された(ただし既知のようにこれらは失敗している。なぜ失敗したかの考察もされているが、失敗したのに「進化」という点に注目)。
現在、科学界を席巻している技術は生物学(本著では主に進化学と脳科学をさしているようだ)と人工知能(いわゆるAI)である。これらの研究により、私たちが「意識」と呼んでいるものの存在が科学的に研究されるようになってきた。人類至上主義、自由主義の根拠となっていた「自己」の「自由意志」というものの正体はなんなのか?最近の研究によると生物はアルゴリズムにより動いているに過ぎないのだと。そのアルゴリズムから生まれるのが「自己」という意識であって、つまりは「自己もまた想像上の物語」ということもいわれるようになった。生命現象(事実)としてそうなのであって倫理的にどうかということは問題ではないのである。
こうして時代は人類至上主義から情報(データ)至上主義の時代へと移行を始めている。ネットワーク(インターネット)上に自分の情報をどんどんアップロードすることにより(もちろんプライバシーを提供することに同意することが前提だが)、自分よりも自分のことを知っていて、より適切に自分の人生の指針(結婚相手や仕事など)を判断して示してくれるアルゴリズム(システム)が登場するだろう(現にSNSの時代とはこういうものじゃないか?)。それで十分幸せな人生が送れるのであれば「プログラムが意識や主観的経験を持たないからといって気にする必要があるだろうか?」。システムにとっては、人類は情報の提供をするだけの存在であり、翻ってそういう人類に人生の指針を与えるというシステムの存在の意味はなんなのか?人類はそういうものを作り出すことを目指しているのか?
こういう未来展望にひっかかる読者がいれば、これでいいのかどうか、ぜひ考えてほしい。それが本書の意義であるという締めくくりであった。
ホモ・デウスとは結局何なのか。ラフがどうとらえたかというと、人類を人類たらしめた要素は未来においてシステム(本書でいうところのアルゴリズム)に代替されうる、このシステムこそがホモ・デウスではないのか(ホモ・サピエンス自らのアップデートではなさそうだよ。つまり人類の進化的後継ではない)。
脳科学の研究を踏まえた「生物はアルゴリズムであり自己なんてものは幻想」という考察はちょっと強引な気がする。確かに脳の活動原理が電気信号と化学物質による情報伝達でありそれが複雑なネットワークを形成しているということはわかっている。でも、どういう情報(刺激)によって、何がどのように作用して出力(行動や意識)が生み出されるのかの仕組みはまったくわかっていないのだ(こういう刺激により脳のこの部分が活動しているからおそらくこの部分が関わっているだろうという程度のことは推測されている)。このわかっていない部分こそが著者の言うアルゴリズムじゃないの?それは全然明らかになっていないし、それを人類が理解できる言語化つまりロジックにするのは現段階では不可能。ここの展開を読んでいて思ったのは「シュレーディンガーの猫」っぽいなぁってこと。ミクロレベルの量子力学の話を、マクロの物理学に持ってくると、おかしな事態になるっていうたとえ話が「シュレーディンガーの猫」なんだけれども、これの脳科学版を読んでいる気もするのだ。レベルの違うことをアルゴリズムという語で強引に引き寄せて結んでしまい論展開が飛躍している。かつて一世を風靡した「生命機械論」を彷彿とさせる面もあるなぁ。
まぁ、本著でもAIのシンギュラリティーはやってくるって前提で話が進んでいるんだけれども、ラフが思うに現状の科学の延長上にはシンギュラリティーはやってきそうにないよ。当分どころかずっとね。シンギュラリティーがやってくるとしたら、まったく異なるとんでもない発想の転換とイノベーションが必要だろうねぇ。
■ ホモ・デウス 上[ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田 裕之]
■ ホモ・デウス 下[ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田 裕之]
以下のような記事もありましたので(以前retweet済み)、紹介しておきます。

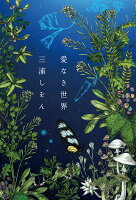
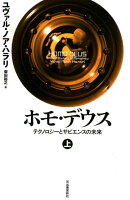

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18a12152.9bb8d6b9.18a12153.ccaa77c5/?me_id=1276644&item_id=10005223&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fryusei%2Fcabinet%2F02768376%2F04271311%2Fimgrc0068140909.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fryusei%2Fcabinet%2F02768376%2F04271311%2Fimgrc0068140909.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




