ぶらぶらと散歩に出かけ、しばらく歩いたのちに、ふと行先も考えずに都バスに乗って(今「天気の子」とコラボレーションしてるんだね)「さて、どこまで行こう」と考える。不忍通りを通るバスだから、根津(言問通りと交差する所)で降りて上野の国立博物館まで歩いてみようと(徒歩15分くらい)。
国立博物館は日本に4館ある(東京(上野)、京都、奈良、九州(大宰府))。上野の国立博物館は東京国立博物館(愛称:トーハク)。上野公園にある一群の博物館、美術館、動物園の中では一番好き。アニメ映画「時をかける少女」にも主要な場所として登場した施設。
■ 東京国立博物館 – トーハク https://www.tnm.jp/
URLがシンプル(シンプルすぎて知らないと本当に公式サイトなのかさえわからない)。tnm は Tokyo National Museum ね。参考までに各国立博物館のトップページへのリンクを載せておきます。
■ 京都国立博物館 https://www.kyohaku.go.jp/jp/
■ 奈良国立博物館 https://www.narahaku.go.jp/
■ 九州国立博物館 https://www.kyuhaku.jp/
kyohaku, narahaku, kyuhaku なのに、東京だけ tnm 。京都と奈良は「go」(government 政府の略、日本政府の機関や省庁の所管する研究所、国立研究開発法人などに対して割り当てられる)を外さないところに、正統性へのこだわりを垣間見るような思いがする。
一番新しい平成館で、特別展「三国志展」をやっていたので、のぞいてみる。本館に外国人が多かった(半分くらいは外人だったのでは?)のに比べると、こちらはほぼ日本人だけでごった返していた。そりゃ日本に来る外国人観光客がわざわざ中国をテーマにした展示を好き好んで見に来ることはないよなぁとおもいながらも、「日本人って本当に三国志好きなんだなぁ」と改めて実感。
中国の正史って、皇帝が歴史家に命じて、前王朝の歴史を書かせるというおもしろい仕組みなんだけれども、これは中国では王朝の交代のことを「革命」と呼び(易姓革命)、王朝の正統性を主張するために前王朝がなぜ滅んだのかを記すということになっているのだ。
「三国志」は正史二十四史の一つなんだけれども、日本で一番有名な「三国志」はおそらく横山光輝のマンガ「三国志」であろう。ちなみに横山マンガは「三国志演義」(明代に成立したエンターテイメント歴史小説)をベースにしている。ところどころに横山マンガの原稿が展示してあるのがほほえましい。ちなみに展示自体は「三国志」をもとにした、最近の考古学的知見の展示。
■ 『三国志演義』とは?正史『三国志』と何が違う?中国で呂布は美男子だと!? – BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)
「三国志」は正史だけれども、「史」ではなく「志」である。学生のみんなは筆記テストで間違えないようにしよう。「日本書紀」が「記」じゃないのと同様ね(「古事記」は「記」)。
■ 三国志の「志」はなぜ「史」ではないのでしょうか。 – 二十四史の中で志にな… – Yahoo!知恵袋
ほかにも今回の展示は結構凝っていて、有名な「赤壁の戦い」に一室を当てており、天井から奥の壁に向かって大量の矢が放たれている状況を再現した意匠は圧巻。

(今回の展示は写真撮影OKなのです)
ふらっと寄っただけだったのに、意図せず素敵な展示を見ることができました。
それと、ミュージアムショップって楽しいよね。仏像写真のクリアフォルダ、仕事で使うとなるとかなりシュール。埴輪の縮小レプリカとか買う人いるのかね?とか思いながらも、心惹かれる(買おうとまでは思わないけれども)。
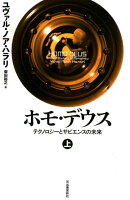

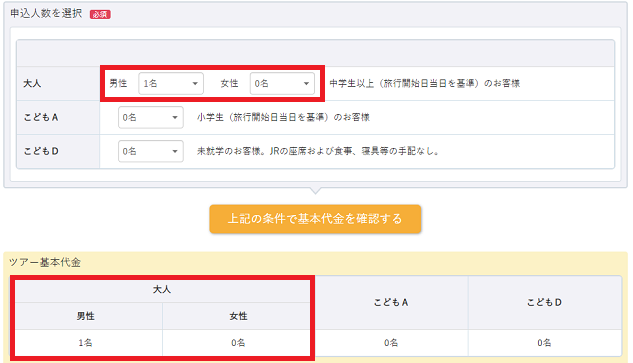
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18be08df.5547d309.18be08e0.85888ff6/?me_id=1211066&item_id=10000360&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoolandmeal%2Fcabinet%2Fitem%2Fitem_00001%2F0843000369_th.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoolandmeal%2Fcabinet%2Fitem%2Fitem_00001%2F0843000369_th.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
