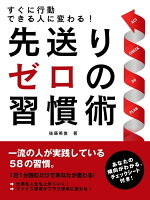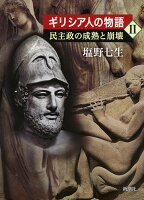どこまでも続く広大な砂漠の果て、そこには古今東西の知識のすべてが収められ、至りし者が神に等しい力を手にできる図書館があるというー長い旅路の末、たどり着いた旅人がひとり。鎖に縛められたその扉を開かんとする彼に守人は謎をかける。鎖は十本、謎も十問。旅人は万智の殿堂へたどり着けるのか!?知の冒険へ誘う傑作長篇!
一言でいうと「なんじゃこりゃ!!こんなものが商業ベースの書籍として流通していいのか?」なんだけれども、各種レビューを見る限りそんなに悪くないんだよね。俺は著者やタイトルが同一の、まったく違う本を読んでしまったのか?
AI石板を携えた旅人が、究極の図書館にたどり着いたのだが、扉は頑丈な鎖で固く閉ざされ、その図書館を守る女性像が謎かけをしてくる。答えを間違えれば殺すという。像が問いかける謎にたいして、すかさずAI石板が情報を検索し該当するエピソード(小話)を再生する。旅人はそのAI石板が再生した話から答えを導く(といっても話のダイジェストを英単語で答えているだけなんだけれども)。
形式としては典型的な枠物語。近代小説においてこの形式は、各小話がそれ自体で完成していて魅力的でないと成り立たない。そして最後にこれらの話を外枠があるテーマでまとめていることが明らかにされて「おぉそうだったのか」となれば「見事!!」となるわけだけれども、まぁそこまでは求められればいいかなくらいにしておこうか。ところが、この小説では各小話はあまり魅力的でない。どこかで読んだような、陳腐で噴飯物のびっくりするくらい道徳的な内容。わざとそうしてあって最後に「実は……」とか期待してみたけれども、そうではなかった。各小話が完成度1として10話あって、最後にまとめられたときに、12(1 x 10 + 2)くらいの効果を生んでくれると枠物語としては成功だと思うんだけれども、この小説は各小話が0.8くらいの完成度で結局最後まで読んで8.1(0.8 x 10 + 0.1)くらいにしかなっていない。
■ wikipediaの「枠物語」の項
やたらと小難しい表現(文章としての表現ではなく難しい漢字を使う単語レベル)を持ち出してくるものの、話自体はたいしておもしろくない。しかも、設定の矛盾とか足りないものとか多すぎ。
敬虔で素朴な宗教信者設定されている人物が、横暴な主人のことを「神のようにふるまう」とか言うか?(必殺ちゃぶ台返し!!)
「護衛対象者には深入りしない。それが彼の流儀だった。しかし一度考え始めると、気になって仕方がなくなった。」なぜ今回の護衛対象に関しては気になってしまったのかを納得させる言及が前後にない。結果としてそれは「恋愛感情」によるものだったんだろうと最後まで読めば推測はできるが、なぜ読者がわざわざ著者の力不足を補わなければならないのか?「彼の流儀」が台無しじゃん。
第九問の問は「ならば、私とは何だ? 私を私たらしめているものは、いったい何なのだ?」だったんだけれども、その答えが「お前をお前たらしめているもの。『Identity(自己同一性)』だ」にはずっこけた。言葉の定義をしただけじゃん……。お前は辞書か。もう、勘弁してくれぇ。
外枠の話も、単にAI石板が問いに対してお手軽に話を再生しちゃっているから、当初主人公と思われた旅人はほとんど何もやらない。うんちく垂れるばっかり(結局この話の本当の主人公は守人の女性像だったわけなんだけれども)。で、徐々に明らかにされたのは、登場人物が全員図書館関係者だったという自己完結の小っちゃい世界観。脱力の極み。しかも問の答えがなんでこんな抽象的な英単語なんだろうと思ったら、その種明かしがこれまた雑。だったら小話の内容なんてどうでもよかったじゃん。
人間は、貧富の差も争いもない平和な理想郷世界を目指す面と(うわ、気持ち悪い。ラフはウェルズの「タイム・マシン(小説)」のイーロイを思い起こした)、嫉妬や抜け駆けや足の引っ張り合いで戦争ばかりしている面があるとのこと。万智の図書館に情報を運んできた旅人は、そんな不完全な人間を見捨て、智の殿堂にともに帰ることを守人に提案するが、彼女は不完全でも前者に向かって進歩していくだろう人間とともに歩むことを決意する。そして旅人もそれに同調して再びあらたな旅に出る。何度も人間の「多様性(多面性)」に言及しているのに、最後は「善悪の二項対立」で片づけてしまっている気持ち悪さ。それって人間の可能性をきちんと評価できていないことにならないか?それが「万智」を名乗ってしまう滑稽さ。
第六問の話はとてもよかったのに(ありふれてはいるけれども)、最後を幽霊オチにしたのはがっかり。あくまでも想像の産物としたほうが人間の可能性や未来を感じさせたのでは?道徳的な上から目線で人間に寄り添っているふりをしているが、実は人間の可能性には思い至っていないような著者の書きっぷりは、少なくともラフの好みではない。
ひどいものを読んでしまったというのが正直な感想。なのに途中で投げ出さずに(何度も挫折しかけたが)最後まで読み切ったんだから俺ってばこの作品の優秀な読者じゃんと思ったり思わなかったり。
■ 叡智の図書館と十の謎(中公文庫)[多崎礼]
■ 叡智の図書館と十の謎(叡智の図書館と十の謎)[多崎礼]【電子書籍】